前回、ふくらはぎに力が入っちゃいけない理由として、
- 第二の心臓を硬くしない
- 自律神経との関係
- 動力源ではない
の3つをあげました。
きょうは、「2.自律神経との関係」についてです。
はじめに答えをいってしまうと、
- ふくらはぎの筋肉は、自律神経の影響を受けやすいので、
- ふくらはぎが硬くなると、自律神経が緊張モード優位となる
ということなんです。
ふくらはぎは自律神経の影響を受けやすい
筋肉の中でも、おもに姿勢の維持のためにはたらく筋肉を「抗重力筋(こうじゅうりょくきん)」といいます。
重力に抵抗して姿勢を維持するという意味ですね。
ふくらはぎの筋肉である「下腿三頭筋」(「腓腹筋」と「ヒラメ筋」を合わせてこうよびます)も抗重力筋のひとつです。
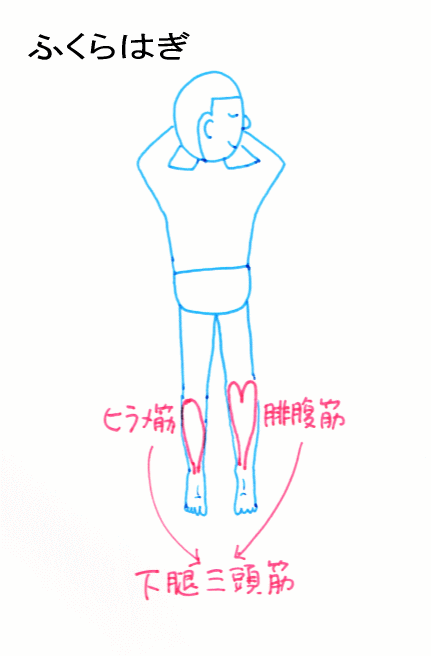
腓腹筋とヒラメ筋、あわせて下腿三頭筋
・・・なんか、急に専門用語ばかりですみません、、、でも続けます(笑)
抗重力筋は、姿勢をキープするために脳とたえず連絡をとっておく必要があります。
そのため、筋肉の状態を察知する“センサー”をほかの筋肉よりも多くもっているのです。
「筋紡錘(きんぼうすい)」というこのセンサーには、自律神経のひとつである交感神経が分布しています。
したがって、抗重力筋のひとつである下腿三頭筋も、交感神経の影響を受けやすい筋肉といえるのです。
整理しましょう。
- 抗重力筋には筋紡錘というセンサーが多くあり、
- 筋紡錘には交感神経が分布しているので、
- 抗重力筋は交感神経の影響を受けやすい
- ふくらはぎの下腿三頭筋も抗重力筋であり、交感神経の影響を受けやすい
ちょっと難しいですかね。
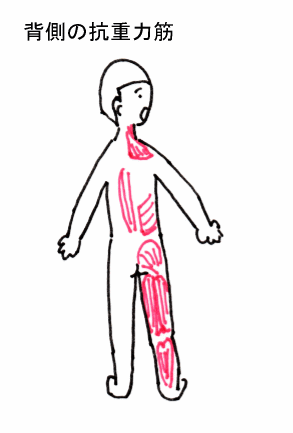
抗重力筋には交感神経の分布する筋紡錘が多い。そのため交感神経の影響を受けやすい。
ふくらはぎが硬い=体が緊張モード
自律神経は、
- 交感神経(緊張モード)
- 副交感神経(リラックスモード)
の二つの神経から成り立っていることは、よく知られていますね。
どちらも大切で、両方がうまくバランスをとることで体は元気に保たれます。
ふくらはぎが硬いとは交感神経優位の状態になっているということです。
これは、体が緊張モードになっていることをあらわします。
逆に、筋肉を緩めることで、リラックスモードの副交感神経優位の状態にもっていくことができると考えられています。
要するに、
ふくらはぎが硬くなる → 交感神経優位・緊張モード
ふくらはぎを緩める → 副交感神経優位・リラックスモード
ということです。
「すぐれた施術家はふくらはぎを触っただけで、その人の状態を知る」といわれますが、それはこういうことだったんですね。
交感神経優位の緊張モードの体であるほど、病気や不調に陥りやすくなります。
ふくらはぎを力ませたくない、硬くしたくない、という理由がご理解いただけたでしょうか。
次回は、もうひとつの理由「動力源ではない」について書きますね。
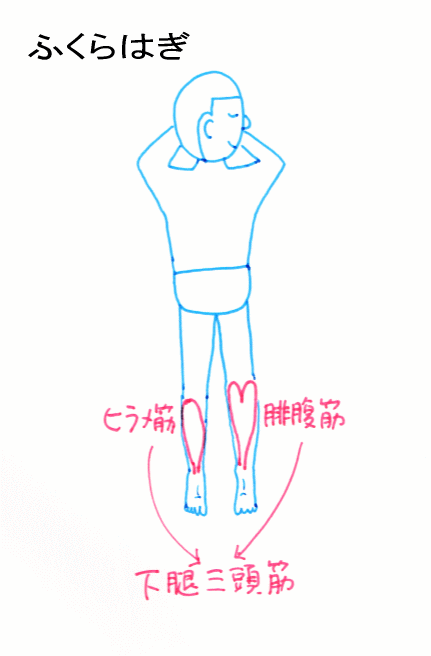
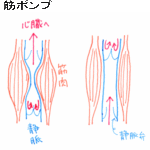
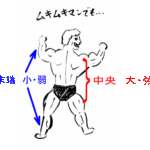
コメント