今回は、私が患者さんにいつも説明する「滑液」のお話です。
「潤滑液」としての滑液
「滑液(かつえき)」って聞いたことがありますか?文字どおり潤滑液のことで、関節の中に常にあります。「関節液」ともいいます。
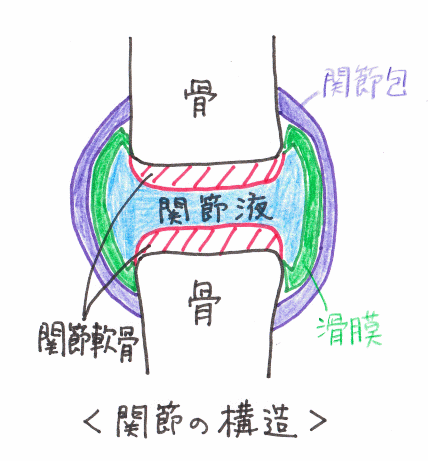
図の青い部分にあるのが滑液(関節液)で、関節軟骨同士の滑りをよくしているんですね。
機械も油が切れたらミシミシきしみますが、関節も同じです。滑液が涸渇したら、きしんで関節軟骨(以下、軟骨)の滑りが悪くなり、軟骨の摩耗が早まります。
ちなみに、よく耳にする「ヒアルロン酸」は、滑液や軟骨に含まれる重要な成分です。潤滑や保水に優れています。
「栄養源」としての滑液
このように、滑液は潤滑液の役割を果たしているのですが、もうひとつ、とても大切なはたらきをしています。
それは、軟骨の栄養補給です。
軟骨には、血管がありません。したがって、血液からの栄養はなく、滑液から栄養をもらいます。
つまり軟骨は、滑液が涸渇すると、滑りが悪くなって傷むだけでなく、栄養補給も乏しくなってさらにダメージを受けてしまうのです。
整理しましょう。
滑液が涸渇する → ①軟骨が摩耗する ②栄養が乏しくなる → 軟骨がさらに傷む
関節軟骨を元気に保つ秘訣
では、どうすればいいのか?(←ここ大事)
実は、滑液は滑膜(図の緑色の部分)で作られ、関節がグニグニと動くごとに、関節内に供給されるしくみになっています。
つまり、関節を動かすことが滑液の供給につながり、ひいては軟骨を元気に保つ秘訣なのです。
わたしが、しきりにラジオ体操をおすすめする理由の一つがこれです。からだを動かしておくことがいかに大切か、ご理解いただけたら嬉しいです!(^^)!
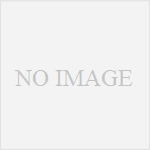

コメント